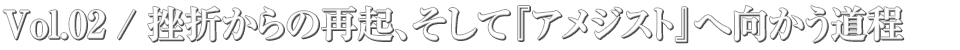■郡島さんが「魂がどこかにいっていた時期だったのかもしれない」とおっしゃったUNLIMITSのメジャー時代を、Junさんはそういうふうに見てたんですか?

Jun「当時のUNLIMITSを聴いてて、ぶっちゃけ『いろんなことを吸収し過ぎだな』って思ってた。それは音楽的なことだけじゃなくて、バンドの見せ方的なところも含めて。俺もメジャーにいたことがあるからこそ言うけど、バンドをやり始めた時の気持ちはどこかに置き忘れちゃって、言われたことをこなさなきゃいけない使命感に対して真面目に取り組み過ぎちゃう部分があったのかもしれないね」
清水「私自身は、メジャーの時のアルバムも凄く好きだし、『いいメロディを聴いて欲しい』っていう一本筋はまったくブレないままやってきたとは思うんですよね。UNLIMITSって、『速くて暗いメロディックパンクバンド』っていう印象が強いと思うんですけど、元々は、いいメロディをちゃんと聴かせたいっていうところが核なんだって思い続けているから。たとえば『NeON』っていうアルバムは凄く壮大な作品になったと思うんですけど、あの作品も、自分の中では筋はちゃんと持っていたと思うんです」
石島「そうですね。僕も、どの時期の作品も誇れるものだと思っているんですよ。ただ、『よくしたい』『前の作品を超えたい』っていう想いのベクトルが、技術とか、僕達の中に元々ないものの方向ばっかりにいっていた感じはするんですよ。で、たとえばプロデューサーさんに訊けば、自分達にない引き出しがどんどん出てくるわけですよ。それを身につけるだけ身につけて、どんどん太って肥満になってしまっていた感じはしますね。で、身につけたものがそれぞれ違う方向を向いちゃっていたというか。やってる当時は、アーティストとしての成長への欲でどんどん技術を詰め込んでいくばかりだったと思うんですよ。で、技術で武装し過ぎたがあまり、自分達の芯にある気持ちが聴いてくれる人になかなか届きにくい感じになってしまっていたのかなって……今は思いますね」
■その芯っていうのが、清水さんもおっしゃっていた「いいメロディをストレートに聴かせたい」っていう部分だと。
石島「はい、そうですね」
清水「……やっぱり、バンドって長く続けることも凄く大事だと思うんですけど、ダラダラやっているんじゃなくて目標を立ててやることが必要だと思っていて。だから、ケツを叩いて自分達にとっての上を目指し続けたいと思うし。だけど、もうバンドは無理かもしれないって思っていた頃はツアーに行くのも嫌になっていたし、あれは人生においての挫折だったんですよ。そういう話をメンバー同士でしたんです。言ったら、自分達がまさかJun Grey Records……(PIZZA OF DEATHレーベル内レーベル)っていうレーベルと関われるとは思ってなかったし、『面白いじゃん、やってやろうじゃねえか』っていう気持ちにさせてくれたのが大きかったんですよね。そこはやっぱりJunさんだったり健さんがやっぱり自分達には魅力的だったし、奮い立たされた部分があったと思います」

郡島「それは凄くあったね。たぶん、辞めたほうが楽だったと思うし、バンドが楽しい瞬間もある半面、それに追われている感覚になってしまってたと思うんですよ。バンドって、一見遊んでいるようでも、ずっと付きまとうものじゃないですか。作品を作ることもそうだし、決まっているライヴへのカウントダウンが常にあるし。それが窮屈だったから、もう解放されたいなって思ってたんですけど、清水も言ったように、これは面白そうだなって思えたんですよね。もちろん自分達はその時にカッコいいと思えるものを作ってきたけど、『自分達はこうだ』って提示するんじゃなくて、周りの期待に応えなきゃいけないっていう気持ちが強くなることで、『いいものを作ろう』っていうことが大事になってたんです。だから、自分達自身が発信したいものを発信することが後になっていたのかなって。そこでまた立ち上がらせてくれたのが、JunさんとKenさんだったなって思いますね」
■Junさんは、UNLIMITSをリリースしたいっていう気持ちが先にあった上でレーベルを作った部分もあるんですか?
Jun「ぶっちゃけ、それは大きいと思う。以前から健に『レーベルやりなよ』って言われてたけど、実際にやってみよう!と思ったのは、UNLIMITSが揺れている状況を見たのがタイミングとして合ったんですよね。で、大月と『やろうよ』って話した時に『もし続けるんだとしたらどういうふうにしたいの?』って訊いたら、『メジャーで学んできたことの要らない部分だけを削ぎ落してやっていきたい』って言ってたんだよね。で、『揺れてはいるけど、やるべきことはわかってるじゃん』って思えたし、だからこそ俺はレーベルをやりたいなって思ったんだよね」
大月「やっぱり、ひたすら吸収してきたことの中にも、いい部分と悪い部分があると思ったんですよね。それのいいところだけを残していけばいいんだっていうのは凄く考えて。たとえばいいところを考えると、メジャー時代で個々のスキルは凄く上がったと思うんですよ。逆に、活動的なところはよくも悪くも守られ過ぎていた部分があったと思うし……だからこそ自分達が我慢していたことや、歯がゆい思いをしていたことを『それは何故だったんだろう?』『なんのために我慢していたんだろう?』って一つひとつ考えていけば、おのずと今やりたいことが見えてくるんじゃないかって思ってたんですよ。それは具体的にどういうことかって訊かれたら、言葉としてはなかなか出てこないんですけど……ツアー一本切るにしてもそうだし、極論、写真を一枚撮るのもそうだし。もしまたバンドが転がっていくんだとしたら、『必要なことだけ残す』っていうのが大事だなって考えてたんだと思いますね」
Jun「実は、ほったらかしにしてたって、バンドはバンドで考えてやっていけるものなんだよね。あまりになんでも教えてくれたりケアされたりすると、今度はバンドが自分達で出していくべきものさえ見失っちゃったりするんだよね。だから、こうしてインディーズに戻ってきて自分達でやることが多くなれば、自ずとUNLIMITSらしさが出てくると思ってたんだよね」
■そこから『アメジスト』の曲作りに向かっていく時に、どういうものを発信していこうと思ったんですか?
清水「音楽的には、どういうふうなものが作りたいっていうのは明確にはなかったんですけど……曲作りのために合宿に行った時に、“リリー”の歌詞が先にできて、『あ、これはいいのできた!』『いけるぞ!』っていうのが自分自身で凄くあったんですよね」
■“リリー”は本当に名曲だと思います。メロディが本当にいいし、シンプルな8ビートでキラキラとした世界観が描かれていく楽曲と歌詞は、今までのUNLIMITSが凄くいいバランス感で出ているものだと思って。
清水「そうですね、“リリー”は自分達でもかなり新境地の曲だと思うんですよ。で、それをまたバンドで合わせた時の衝動が凄くて。そういうふうに、自分達の作った曲自体が自分達の自信になっていったんですよね。他にも、たとえば“アネモネの夢”とかは初めて群ちゃんが作曲した曲だし」
■なるほど。“アネモネの夢”も、ダンサブルなリズムとUNLIMITSらしいちょっと憂いのあるメロディが絡む新鮮な曲ですよね。
清水「私はそういう曲達も凄く好きなんですよね。そういう新しい可能性がまた出てきたことによって、まだ自分達はやれるんだって、だんだん思えてきた感じなのかもしれないです。やりつつ立ち上がていったというか」
郡島「曲を作っていく時点で特別改まって考えることはなかったんですよ。アレンジも悩まずにできたことのほうが多くて。それは、たとえば『NeON』の時にプロデューサーさんに教わった技術的な部分を自分達で生かせたからだと思うんですけど」
■吸収してきたものの中で、必要なものを自分達で選択できるようになってきた。

石島「そうですね。今言われたように、何をどうしようかを決めるのは自分達だけっていう環境でやっていたので、『どれがカッコいいのか』っていう選択の場面になった時にスッといけたんですよ。で、それが形になった時に『やっぱり正解だった』って自分達でも言えて。そうやって、自分達らしさを取り戻せたと思うんですよね。“リリー”も、いろんな人から『いいね』って言ってもらえているし、今凄くいい状態になれているって自分達でも思えていて」
■Junさんは、UNLIMITSがこの作品を作っている時はどういう立ち位置にいたんですか?
Jun「UNLIMITSに関しては、もう何年もやってきたバンドだし、ノウハウも学んでいるから………一応レーベルプロデューサーになってるけど、もう俺は『プロデュースしねぇ!』って思って(笑)」
石島「ははははは!」
■「はい、自由にやって!」っていうのがJunさんのプロデュース法だったと(笑)。
Jun「そう(笑)。今まで外部の人ともたくさんやり合ってきたバンドだから、今は逆に、100%自分達だけでやることが必要だと思ったんだよね。あとは、レコーディングに入る前に、合宿でできた新曲――“エターナル”とか“リリー”とか“スターライト”とかを聴かせてもらった時点で『これは絶対にいいものが作れるわ』って確信できたから」
■“エターナル”はいわゆるUNLIMITSらしい剥き出しの衝動が疾走してる曲だし、“リリー”みたいに純粋にメロディが抜けていく曲も、“スターライト”みたいに合唱できるくらいポップな曲も、UNLIMITSが広げてきた音楽性がバランスよく出てる曲ですよね。
Jun「そう、そう。だから、安心したんだよね。レコーディングも2回しか行ってないし――」
大月「1回です」
清水「はははははは!」
■(笑)。話にも出ましたけど、アルバムの冒頭が“アメジスト”“エターナル”っていう、速いビートでマイナーコードが走る楽曲になってるんですけど。こういう、いわゆるUNLIMITSっぽいメロディックパンクがアタマから来るのは凄く久しぶりで。やっぱり衝動的なものが爆発して出てきた感じだったんですか?
清水「確かに『原点回帰』『初期衝動』っていう言葉を掲げてはいたんですけど、この辺の曲は……正直、苦しみましたね(笑)。初期衝動は初期衝動でも、やっぱり以前のものを超えていかなくちゃいけないと思ったし」
■一番衝動的でストレートな「ザッツUNLIMITS」な曲だからこそ、ハードルが高かった?
清水「そうですね。初期衝動だけど、それだけじゃつまらないし。だから“エターナル”は何度もメロディもコーラスも練り直したし、かなり難産でしたね(笑)。“アメジスト”も凄く短い曲ですけど、直前で全然違う曲みたいに組み立て直したし。イントロのアルペジオだけできてたんですけど、1分間にどれだけUNLIMITSらしさを詰め込めるかっていう挑戦をしたので、それが大変で」
■清水さんの曲の作り方自体は昔から変わってないんですか?
清水「そうですね。私は、常に曲やメロディの断片を作っているタイプで。それをパズルみたいに組み合わせていく感じなんです。だけど、11曲目に入っている“君に読む物語”とかに関しては、機材車の中でまるごと完成したんですよ。これはピアノも入れたんですけど、東京から八戸間で、ガレージバンドをピシピシピシッって(笑)」
石島「9時間くらいか(笑)」
清水「そうそう。で、高速を降りて聴いて、『あ、いい』って(笑)。単純に、でも、前だったら機材車で作るっていうことはなかったんですよね。きっと、時間の使い方が曲作りのほうにいき始めてるのかもしれないですね」
■それこそ、先に「自分達の生活」の話がありましたけど、それがそのまま音楽になり始めている感覚というか。
清水「ああ……確かに。だんだんそうなってきているのかもしれない。それこそ初期の頃なんかは、めちゃくちゃ時間かかってましたから。それこそ、ガレージバンドもMTRも何も使えなくて、ずっとギターの弾き語りでメンバーにも聴かせていたので、バンドでも伝わり辛いし(笑)。しかも、自分で作って『いいな』って思っても、自分だけでボツにしちゃうことが多くて。自分に刺さるものじゃないと出したくないっていうのはずっと変わってなくて……でも、合宿に行ったことでそういうネタもメンバーにすぐ聴かせられたし、それがよかったと思います。悩んで追い込んだ先でパッとできる瞬間が合宿にはあるんですよね。“リリー”も、悩んでグーッとなってる時に郡ちゃんが歌詞をパッと持ってきてくれたから、10分くらいで曲が浮かんで。そういうモードになるのが大事だなって思いましたね」

■そうやって作っていく曲を作っていく上で、一番気にしていたところとか、メンバー自身の基準になるのはどういう部分だったんですか?
大月「それこそさっきの話なんですけど、メジャーでやっていた時は特に、『難しいことをやるのがカッコいい』って思っていた節があったんですよ。そうなると、シンプルなものが不安になってしまいがちになっていって。たとえばコード一発鳴らしてるだけで成立していてカッコいいものなのに、シンプル過ぎて『これでいいのかな? もっと凝らないといけないのかな?』って思っちゃうクセがついていたと思うんですよね。そこで、シンプルでもそれが曲に合っていたらそれでいいじゃん!って言えるようにしたのが、特にギターに関しては一番大事にしたところで。それが、自分達にとって削ぎ落とすっていうことだったんだと思いますね」
INTERVIEW BY 矢島大地(MUSICA)
Vol.3 へ続く